
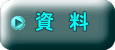
中国・南宋時代の思想家として有名であるが、哲学的な文章を書いただけでなく、詩も作っている。本人の意識としては、「思想」とか「文学」とかで制限することなく、あらゆるものに着手し精通した。詩については、ある一時期に作りすぎた結果、作詩を禁止することを誓い、しかし、それをすぐ破ることとなった。朱熹は、どういう観点から作詩を禁止しようと考え、また禁詩することを止めたのか。これには、「人性(じんせい)における天理と人欲の対立」も関連しており、このことに迫りながら詩というものをどうとらえていたのかについて、話をしたい。
2 衡山(湖南省)への旅――禁詩の誓い
さて、朱熹は、乾道三年(一一六七)三十八歳のとき、八月から約四ヵ月間にわたる湖南への旅で二百余篇の詩・詞を詠じた。特に友人二人(張栻(ちょうしょく)・林用中)との南嶽・衡山(こうざん。五名山の一つ)に登ったときには、七日間で五十篇前後の詩詞を詠じた。そして、衡山を登り終えた帰路に、禁詩を誓った。
その様子は、張栻の著述「南嶽唱酬序」によれば、「数日間、作詩にふけりすぎてしまったため、自らの志(し)を喪(うしな)ってしまうことを懸念して、翌日から作詩を禁じることとした。これ以降、うたいたいものがあったとしても、もう詩には見(あらわ)さないことを約束した」。
3 葛藤、そして誓いの解除
朱熹の記した「南嶽遊山後記」によれば、「衡山の景色が素晴らしいため、どこを見ても詩にうたいたくなってしまうが、前日に禁詩の約束をしている。しかし、張栻との別れの日が迫っていることを考え、皆に提案してみた。「詩を作ることは、もともと善くないという訳ではない。詩を作る愉しさに没頭してしまって、欲するまま望むままに、情に流れてしまい、自らの本心や志を喪い、心を乱してしまうことを心配するだけである。お互いにばらばらに別れるが、詩でなければ伝えられない懐(おも)いというものもある。そうであれば、やはり度を超した約束と言える禁詩を罷(や)めるべきではないだろうか」。この提案に対して、皆は賛成してくれた。張栻は、早速詩を作り贈ってくれ、これに友人達も各々詩で応えた」。
再び朱熹が友人達に言ったことは、「先日の約束は度を越していたが、これも、詩を作ることが愉しくて愉しくて仕方なく、心の欲するままに、情に流れてしまって、心の本来のあるべき姿を喪ってしまうことを懸念してのもの。そのことを自らの誓(いまし)めとしてしっかりと忘れないでいれば、作詩というものは、本当は良いものなのだ。なぜなら、作詩には本心を志として述べることで、鬱屈(うっくつ)した思い(湮鬱(いんうつ))をのびやかにし、自らの心を穏やかにしずめる(優柔(ゆうじゅう))という効果があるのだ」と。このように、朱熹は、一方で詩を詠むことの効果として「優柔」ということを特に重視した。
朱熹は、友人・択之(たくし。林用中)が作ってくれた韻目「生」の警しめの詩に対して、次の一首を唱和して謝意を表し、また、帰途を共にする伯崇(范念徳)にこれを示した。
| 擇之所和生字韻語極警切次韻謝之兼呈伯崇 択之和する所の「生」の字の韻語極めて警切韻を次ぎて之に謝し兼ねて伯崇に呈す 朱 熹 不是譏訶語太輕 是れ語太(はなは)だ軽きを譏訶(きか)するにあらず 題詩只要警流情 詩を題するには只だ流情を警(いまし)むるを要す 煩君屬和増危惕 君が属和(しょくわ)を煩(わずら)はして危惕(きてき)を増す 虎尾春冰寄此生 虎尾春冰此の生を寄す |
4 朱子は「心」を最重視
前後するが、朱熹は、キリストのような宗教の教祖とは別の形で、後世に対して非常に大きな影響力を与えた人物であったと思われる。中国から日本、朝鮮、ベトナム、そしてモンゴル、チベットと、東アジア全域に朱熹の発想や考えが伝わり、朱子学が広がった。時代としては、朱熹が亡くなった後の十三世紀半ば頃から定着し近代が始まる十九世紀まで、朱子学が色濃く影響を与えた。そして、日本もそうだが、この朱子学を批判対象とすることによって近代化を模索することにもなる。そのため、朱子学というと封建思想なるものが注目を浴びてしまうが、朱熹が最も言っているのは「人の心」ということ。いかに心の平静を保って物事を順調に進めるか、と言ったことを重要視し、こうした考えが影響を与えた。
5 「心」の修養――「已発」と「未発」
ところで、自ら心をどうみがくか、修養(工夫)をどう進めていくかは、朱子学共通のテーマである。少し哲学的な話になってしまうが、朱熹は心を二つに分けてとらえた。日本人が共有している概念と結びつくところがあるが、一つは「已発(いはつ)」、何かに感応しているときの心、何かにとらわれて動いているときの心。もう一つは「未発(みはつ)」で、心が何ら動いていない状態。朱熹が衡山の旅をしていた三十八歳の頃は、前者の已発、動いているときしか心は修養できないもので、心に兆してきた自覚できるものだけを修養の対象とし、それを反省材料とみなすことを考えていた(いわゆる旧説)。「情があふれてしまい、何かに感応しそちらに注目してしまうのは問題であり、そうした心がとらわれたものから脱却するというのは、已発の修養となる」とした。その後、四十歳に至って新たな「未発已発説」を唱えた。すなわち、「未発のときも修養の対象とする。何かの欲望というものに対しても、我慢をするというのは已発のレベルでのことであって、未発の修養ということでは、心の本体、志をキチッと確立して物事に惑わされないこと」が重視された。
6 多い自警詩
朱熹には、張栻と交流して已発の修養を重視していた頃には、自らを警めた「自警詩」が多い。次は、その一例。北方の金国に対する主戦論を主張した南宋の政治家・胡銓(こせん)が左遷され、十年後に許されて帰る途中の宿泊先で壁に書き付けた詩を、朱熹が目の当たりにして詠じた自警詩である。
| 宿梅溪胡氏客館觀壁間題詩自警二絶 其二 梅渓胡氏の客館に宿し壁間の題詩を観て自ら警む二絶 其の二 朱 熹 十年湖海一身輕 十年湖海一身軽し 歸對黎渦却有情 帰りて黎渦(れいか)に対して却て情有り 世路無如人欲險 世路人欲の険に如(し)く無し 幾人到此誤平生 幾人(いくにん)か此(ここ)に到りて平生を誤る |
7 「平中に優柔する」
これまで触れた朱熹の観点と言うものをまとめてみると、詩を詠じることによって、情に流れてしまうことがある。詩をよむ愉しい気持ちを増幅させてしまい、時宜をわきまえずに没頭することによって、人としての大事なことを喪ってしまう。そこで、禁詩を思い立った。しかし、こうした警戒感を持ちながら、一方、自らの心を育てるには、詩と言うものが大切であり、詩を詠じることによって自らの心をゆったりとさせ、穏やかに保つことができると考えた。朱子学は人の心を涵養する学問であり、朱熹は作詩において、「湮鬱を宣暢する」、鬱屈(うっくつ)した、塞(ふさ)ぎ込んだ心をのびやかにしてくれる要素があることと、この「平中に優柔する」こととを重視した。以上が、「禁詩」における葛藤からうかがえる朱熹の詩と心に対する考え方である。
◇
上記の要旨につきましては、松野敏之先生のご校閲を賜りました。取分け学年末のご多用中ながら、温かなご助力をいただくことができましたことに、深甚なる謝意を申し添えます。