| |
驚いたのは司徒廟を訪ねたとき。庭園に樹齢二千年と言われる柏の大木が、石に支えられ横たわっているがまだ青々とした葉を付けている。ここでじっと実に呉の時代から世の趨勢を見てきたであろうが、今も世界のあちこちで浅はかな人間達が争いを繰り返しているのをどう思っているのかと聞きたくなりました。
|
| |
司徒廟古拍 加藤 武
故園花鳥惜春情 故園の花鳥 春を惜しむの情あり
古木蕭條枕石横 古木蕭条として石を枕にして横たわる
聞道千年看此地 聞道(きく)ならく 千年此の地を看まもりしと
問公何世太平迎 公に問う 何れの世にか太平を迎ふと
|
 |
| |
|
|
| |
司徒廟古柏 河野幸男
淸奇古怪似虯龍 清奇古怪 虯龍の似く
錯節盤根天界衝 錯節盤根 天界を衝く
應有悠悠千載志 応に有るべし 悠々 千載の志
文人到必詠威容 文人到れば必ず威容を詠ず
|
 |
| |
司徒廟前有一樹 河野幸男
借問正名芳樹葩 借問す正名 芳樹の葩
客人笑答紫荊花 客人笑って答ふ 紫荊の花と
春風駘蕩淸香遍 春風駘蕩 清香遍し
萬朶千紅競麗華 万朶 千紅 麗華を競ふ
*紫荊花…或言、花蘇芳
|
 |
| |
|
|
| |
柏葉葱葱 尚堂 宮崎三郎
古柏盤盤姿怪奇 古柏盤々 姿は怪奇
身横腰裂葉猶滋 身は横たはり腰は裂くるも 葉は猶ほ滋し
四株賜字二千歳 四株 字を賜りて二千歳
廟裏風柔春日遲 廟裏 風柔らかく 春日遅し
|
 |
| |
|
|
| |
林屋山莊 原 正
田舎盤餐肉與蔬 田舎の盤餐 肉と蔬と
卓邊珍膳旨肴餘 卓辺の珍膳 旨肴余る
凞凞村媼頻供應 凞々として 村媼は頻りに供応すれば
正似家鄕覊旅閭 正に家郷に似たり 覊旅の閭(むら)
|
 |
| |
|
|
| |
西山島熙春 尚堂 宮崎三郎
山村飯店午餐堂 山村の飯店 午餐の堂
多少珍羞添一觴 多少の珍羞 一觴を添ふ
歸路緩行花和醉 帰路緩行すれば 花 酔いに和し
梨雲紛郁放春芳 梨雲紛郁たり 春芳を放つ
|
 |
| |
|
|
| |
鷲野直美
翌日もトラブルがありました。昼食を林屋山の近くの農家が経営するレストランで頂いたのですが、そこでお借りした御手洗いが・・・。
外へ出ようとしたところ、扉が開かない。開けようとして解錠しようとしたら、鍵が穴からはずれてしまう。しかも、持ち手から九十度曲がった状態で。「ええっ、どうしよう。」と曲がった部分を指で挟むとなぜか簡単に元に戻って平らに・・・。鍵穴に収めて右へ左へと回し、悪戦苦闘の末解錠に成功。「流石中国の鍵、役に立っているのかいないのか」と考えつつ席にもどった次第。しかし、そのことを黙っていた為、知らずに後から利用した方々が同じ被害に・・・。こんなことなら、昔のように、扉も鍵もないオープンエア方式の方が余程、安心なのではと思いました。そこに鍵があれば、何も考えずに、反射的に施錠してしまう私たち。この国にいる間は配慮が必要だ、とも思いました。はっきり言えば「信じるな、中国の鍵!」です。昔は、いろいろ壊れたり外れたりしたのでいつもドライバーを持っていました。今もやはり必要です。
今回の吟行会の景色の美しさ、旅程の楽しさ、交流会の充実具合などは、風流才子の千漢連の皆様がお伝えくださると思いますので、それはお任せ致します。私の駄文はこれまで。次回があれば、また参加させて頂きます。
|
| |
林屋受難
江村靜晝淨房隈 江村の静昼 浄房の隈
誰識門扉有大災 誰か識らん門扉に大災有るを
吹影鏤塵私久闘 吹影鏤塵 私かに久しく闘うも
鑰匙曲撓奈何開 鑰匙曲撓して開くを奈何せん
|
 |
| |
|
|
| |
青木智江
二日目、太湖の島「西山」に車で橋をわたって行く。太湖最大の島で、南北11㎞、東西15㎞ある。中原から逃れてきた人々の末裔が住む村落などがあり、杏子や桃や梅の木が花を満開に咲かせている。今、すがすがしい風が吹いていて、車の中にも微かに香りが漂ってくる。車が通る大通りの所々にお茶屋があり、「碧螺春茶」という看板が目に付く。この地方の有名な緑茶だそうだ。梅や杏子、桃などの樹の下にお茶が植えられていて、お茶にその果物の香りが移り、良い香りがりがするのだという。
|
| |
碧螺春茶
陽春村路鳥啼盈 陽春の村路 鳥啼盈ち
果樹成圍茶圃明 果樹囲を成して茶圃明らかなり
茅店茗煙香馥郁 茅店の茗煙 香り馥郁
杏桃加味一甌淸 杏桃味を加えて一甌清し
|
 |
| |
|
|
| |
第九洞天 河野幸男
歩歩低頭入洞天 歩々 頭を低れ 洞天に入る
岩漿滴滴曲池邊 岩漿 滴々 曲池の辺
深潭幽谷人蹤滅 深潭 幽谷 人蹤滅す
何處不知棲水仙 何れの処か 水仙の棲むを知らず
|
 |
| |
|
|
| |
遊林屋山第九洞天 芳野禎文
天工鍾乳柱如林 天工の鍾乳 柱林の如し
七處點燈巖影森 七處 灯を点じて巌影森たり
冬暖夏涼仙氣有 冬暖かく夏涼しく仙気有り
一來聖地信心深 一たび聖地に来たれば信心深し
|
 |
| |
|
|
| |
青木智江
林屋山荘での昼食の後、明月湾に移動する。2500年前、春秋時代に呉王夫差と西施がやってきて明月を眺めたところから、この名前がついたらしい。ここにある村は三方が山で囲まれ、一方が太湖に面し、一年中緑が美しく、桃源郷の趣がある。
|
| |
古 村
靑山風暖氣蒼蒼 青山風暖かにして気蒼々
獨歩孤村一徑長 独り孤村を歩めば一径長し
啼鳥關關何處起 啼鳥関々何処より起る
桃花流水是仙鄕 桃花流水是れ仙郷
|
 |
| |
|
|
| |
蹊山 薄井 隆
太湖最大の島である西山には、林屋山、第九洞天、明月湾などの観光名所がある。先ず第九洞天の洞窟を巡った後、林屋山に上る。喘登一刻、道観の駕浮閣が建つ山頂からは太湖が一望された。渺茫と広がる湖面は淡煙に霞み、幾つかの島影が黛を刷いたように浮かんでいる。穏やかな昼下がりの日射しの中、登ってきた疲れも手伝って何か眠気を誘われるようなひと時だった。
林屋地区は午前中に立ち寄った司徒廟のある香雪地区と並んで屈指の梅の名所だそうである。今は梨の花が真っ白に咲き誇り、菜の花と共に江南の春を鮮やかに彩っていた。
|
| |
太 湖
小丘登盡倚欄干 小丘登り尽くして欄干に倚れば
一望平湖水渺漫 一望の平湖 水渺漫たり
島影兩三輕靄裏 島影両三 軽靄の裏
細漣如睡正春闌 細漣睡るが如く 正に春闌
|
 |
| |
|
|
| |
蹊山 薄井 隆
明月湾は林屋から更に南下した島の南端に位置する古村で、呉王夫差と西施が此処で観月したことからこの名が付
いたという。寵姫を伴っての観月の宴、皎々たる清光の下で王の得意もここに極まったことだろう。思わず「今人不見古時月 今月曾経照故人」の名句が口をついて出た。
狭い路地を挟んで明・清時代の建物が軒を連ね、古色蒼然とした光景はまさにタイムトリップしたかの感がある。 村の一角に越王勾践の謀臣であった范蠡が蓄財の守護神として祀られていたのには驚いた。聞けば王の下を去って商人に転身し、やがて大富豪となってこの地に隠棲したのだという。呉越の興亡史に登場する夫差や西施、范蠡などがこんな小村にも名を留めているのを知り、歴史のロマンを感じること頻りであった。
樹齢千年という樟の大木や石を積み上げた古い船着き場なども古村に趣を添えていた。
|
| |
明月灣
聞説呉王伴美姫 聞説(きく)ならく 呉王美姫を伴ひ
共觀明月太湖涯 共に明月を観る 太湖の涯り
玲瓏影入水搖漾 玲瓏 影入りて水揺漾
握手觸肩應忘時 手を握り肩を触れ応に時を忘るべし
|
 |
| |
|
|
| |
蕗山 清水義孝
車中鷲野先生の「蘇州の詩」の解説を聞きながら、太湖大橋を渡り西山(現在の名称は金庭)に入る。あちこち廻り明月湾古村に到着。その昔、戦火から逃れてきた人々が住みついたといい、石を敷いた小道が縦横に続いている。聞けば、旧家四大姓といわれる旧家があるという。記憶相違がなければ、呉、秦、鄧、王の四姓と聞いた
|
| |
明月灣古村
連軒屋舎洞庭傍 軒を連ぬ屋舎 洞庭の傍ら
狹路縱横幽寂鄕 狭路縦横 幽寂の郷
小伯館中懷往事 小伯館中 往事を懐へば
紅梅自發占春陽 紅梅 自から発いて春陽を占む
*小伯=范蠡の字
|
 |
| |
過洞庭湖古埠頭
呉王曾到洞庭頭 呉王曽て到る 洞庭の頭
墨客文人斯繋舟 墨客文人 斯に舟を繋ぐ
今只空餘淸淺水 今は只 空しく余す清浅の水
碧波溶漾尚留愁 碧波溶漾 尚ほ愁を留む
|
 |
| |
|
|
| |
名月灣懷古 田中 洋
夫差舟上伴西施 夫差 舟上 西施を伴ひ
忘政晴天賞月嬉 政を忘れ 晴天 月を賞して嬉(たのし)む
勾踐粉身嘗胆久 勾践身を粉にして嘗胆すること久しく
亡呉終併太湖馳 呉を亡ぼし終に太湖を併せて馳す
|
 |
| |
|
|
| |
明月灣頭 尚堂 宮崎三郎
太湖浩蕩漾淸漣 太湖浩蕩 清漣を漾はせ
點點靑螺似浮天 点々たる青螺 天に浮かぶに似たり
遙想呉王觀月夜 遥かに想ふ 呉王観月の夜
姮娥西子共娟娟 姮娥 西子 共に娟々たらん
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
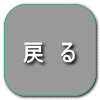 |
| |
|
|

